
この本について
「面白きことは良きことなり!」
これがこの物語の全てで、もっと言えば森見登美彦作品の全てである。
と、言って終えてしまってもいいんだけど、いささか乱暴なのでちゃんと書くことにします。書くことにするけど、この物語はあんまりそれっぽい理屈をつけて語るべきじゃないとも思う。語るに落ちてしまう。だから、つべこべ言わずにとりあえず読んでくれ、と最初に言っておく。
あ、今回はたぶん結構ネタバレを含みます。
このお話では、狸と天狗と人間の、京都における三つ巴が描かれている。狸は化かす、天狗はふんぞり返る。人間は狸を鍋にし、天狗を畏れる。
さっき書いた通り、主人公は狸である。狸界の名家、下鴨家の三男、下鴨矢三郎。彼と彼の家族と、それをとりまく狸、天狗、人間が一大騒動を繰り広げる。狸・人間・天狗、どれをとっても変なやつばかり登場する。
下鴨家の兄弟たちはみんなへなちょこで、長兄は肩肘張っているが非常事態に弱く、次兄は蛙に化けたっきり井戸の底から動かず、弟は弱虫で化けてもすぐ尻尾を出す。そして矢三郎は面白いことにしか興味がなく、面倒ごとばかり引き起こしている。
そんな下鴨家を目の敵にしているのは夷川家の狸たち。金閣・銀閣は親衛隊を引き連れて意地悪ばかりするが間が抜けている。その妹である海星は矢三郎の許嫁だがなぜか姿を見せず、たまに声だけ現れては罵倒と助言を残していく。3匹の父親である早雲は下鴨四兄弟の叔父だが、黒幕めいて何らかの陰謀に関わっているらしい。
矢三郎が慕う天狗、如意ヶ嶽薬師坊は、かつては赤玉先生と呼ばれ、天空を謳歌する大天狗だったが、今では失墜してボロアパートに隠居している。すっかり力は失っているのにプライドだけは高い。矢三郎が世話を焼かなければろくなものを食べず、手当たり次第具材をぶちこんだ不気味な粥ばかりすすっている。風呂も嫌いで、矢三郎が連れ出さなければ絶対に入らない。そもそも自室の風呂場を壊している。常に眉間にしわを寄せ、赤玉ポートワインを舐めて日々を過ごしている。
赤玉先生失脚の原因を作ったのは、弁天と呼ばれる人間である。全盛期の赤玉先生がさらってきたこの女子は、先生に天狗の術を手ほどかれ、全てを身に着けたところで先生を蹴落とした。絶世の美女だが、天狗よりも天狗的に気の赴くまま闊歩するため恐れられている。金曜倶楽部という謎の団体に所属し、忘年会で狸鍋を食らうため、狸からは特に恐れられている。赤玉先生は今でも弁天に想いを寄せているが、弁天はめっきりボロアパートには顔を出さない。
こいつらが何をするかというと、まあ色々とするんだけど、基本的には面白いことを求めて、あるいは面白いことにつられて右往左往するだけである。特にこの本の前半は。いたずらしたり、されたり、空飛ぶ納涼船でバトったり、金曜倶楽部に潜り込んで肉を食らったり、赤玉先生を風呂に入れたり。
そんな感じで割と呑気な話なんだけど、実は矢三郎たちの父親は弁天たち金曜倶楽部に鍋にされたせいで死んでたりする。さらに母親のかつての恩人まで金曜倶楽部に属していたりする。
弁天は「食べちゃいたいくらい好き」と矢三郎に言い、実際に鍋にしようとしたこともある。「私に食べられるあなたがかわいそうなの」「でも食べてしまうのよ」と言って、矢三郎の父を食ってしまった。
矢三郎は弁天が父親を食ったことも知っているけれど、「食われてはたまらん」と言いつつ行動を共にしている。
矢三郎の父は、鍋の具材として捕まっても「一匹の狸としての役目はまっとうした」「食いたければ食うがいい」と言い、「自分は不味くないだろうか」などと心配さえする。
食い食われの関係なのに、なんだか達観しているのだ。狸側は当然死にたくないと思っているし、父親を亡くせば泣いて悲しみもするが、「狸であれば鍋にされることもある」とも思っている。人間側も狸に情を寄せつつ、やはり「狸であれば鍋にされることもある」と言って狸鍋を食らう。
独特のからっとした死生観が、少し心地悪く、少し快い。
物語の後半は、結構血生臭く陰湿な陰謀が渦を巻き始める。早雲のたくらみが明らかになって、矢三郎の家族が狸鍋にされそうになる。前半からは一転、サスペンス然とした展開になってくるけど、それを全てぶっ壊してめちゃくちゃにするような結末は実に森見登美彦的で痛快だ。家族の生死がかかっている場面でもシリアスになりきらず、どこかのほほんとした雰囲気が漂っているのも森見さんらしい。割と読んでて胸糞悪いところもあるけど、読後感は最高に爽快だった。
『有頂天家族』では、「阿呆」という言葉が繰り返し出てくる。いたずら合戦も、狸鍋の餌食になるのも、「阿呆の血のしからしむるところ」らしい。ここで言う阿呆っていうのは、もちろん文字通りの意味もあるんだけど、「面白く生きようとする精神」かな自分は思った。
「おもしろき こともなき世を おもしろく すみなすものは 心なりけり」
って感じ。
これは狸の話だけど、俺たち人間にも「阿呆の血」は流れているはず。この世を面白く住みなすのだ。阿呆に生きよう。
以上が感想です。
森見登美彦作品について
森見登美彦さんの物語を読んだのは久しぶり。森見さんの本は、そんなにたくさん読んだわけではないけれど、どれも印象深い。
『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話体系』が特に有名かもしれない。この2作品はすごく似ていて、「京都が舞台の」「腐れ大学生を主人公とした」「黒髪の乙女との恋を描く」「奇想天外妄想爆発恋愛ファンタジー」と紹介すれば両方にあてはまる。共通して登場するキャラクターもいて、両者まとめて森見登美彦ワールドという感じ。
とはいえ、これはこの2作品だけに言えることじゃなくて、森見登美彦作品はどれも似たような雰囲気が漂い、世界観も共通している。「もっとこの世界に浸りたい」と思った時点で、森見さんの術中にハマっている。
ちなみに、一番好きなのは『恋文の技術』です。知名度では劣るかもしれないけど、『夜は短し』『四畳半』だけじゃもったいないよ。
それから、森見さんの擬態語がすごく好きだ。「狸たちがうごうごしている」とか、「ぷりぷりとした可愛さ」とか。世界観を作る重要な要素の1つだと思う。思いつきそうで思いつかない表現ばかり。何より字面がかわいらしい。
森見登美彦という人は、本当に頭がいいんだろうなとつくづく思う。ごく普通の一文にわくわくさせられる文章なんてそうそうない。帯のコメント、「登美彦氏史上、これまでになく毛深く、波乱万丈。」なんて何気なく書いてるけど、何気なく書けねえよこんなん。
森見さんは京大出身らしい。そのせいか、変人の京大生がそのまんま大きくなったような印象を文章からも感じるけど、これは結構とんでもないことだと思う。俺たちのイメージするような、「頭がいいけど阿呆な大学生」みたいなのをそのまま表現するのって、ただ賢そうな文体を使うことよりもただ脱力系な言葉を垂れ流すよりも断然難しいはずだ。頭のいい人の文章だ。俺には書けないと思わされる。
その他
この本、読み始めてから狸が主人公だってことを知ってびっくりした。タイトルは知ってたけど内容は全く知らず、ブックオフの108円コーナーで見つけてラッキーつって買っただけだったので、きっとまた腐れ大学生の話なんだろうと思っていた。
でも改めて見ると、
表紙にめっちゃ狸いるんだよね。これでまたびっくりした。緑と茶色の何かしらの模様だとしか思ってなかった。なんで気が付かなかったんだろう……。
後半を一気に読んじゃいたくて、初めてわざわざカフェに行って本を読んだ。
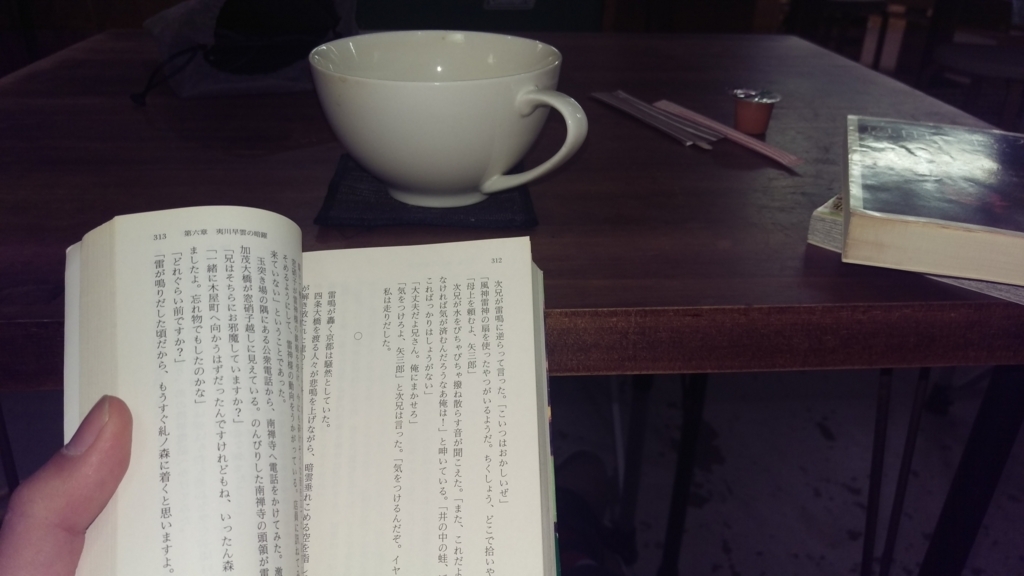
古本カフェというのに前から行ってみたかったっていうのもある。落ち着いて読めてよかったけど、時間が深くなるにつれて常連っていうか身内っぽい人が増えてきて若干居心地がわるかった。でもまた行くと思う。
『有頂天家族』を読み終わった後、店に置いてあった石田衣良の『夜を守る』を読んでたんだけど、半分くらいしか読めなかった。次回行くときには全部読むつもり。
石田衣良は一時期結構読んでたけど、最近はすっかり手を出さなくなった。なんとなく、全部同じような感じに思えてしまったような覚えがある。伊坂幸太郎とか誉田哲也とかと同じ箱に入ってる。
あと、この記事ではなんとなく見出しを使ってみたんだけどどうだろう。あんま意味ないような気もする。
おまけ
いい路地。

こういう写真を載せると、場所が特定されたりするんだろうか。まあ、別にいいや。そもそも読んでる人も大していないしね。
それでは。
